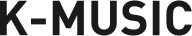韓国ソウルを拠点に活動する4人組バンド・Soul delivery(ソウルデリバリー)。そのバンド名には、音楽ジャンルとしての「ソウル(Soul)」をリスナーに届けたいという明確な意思が込められている。2022年のデビュー直後から、1stフルアルバム『FOODCOURT』、続く2nd『Peninsula Park』に収録された「Whiskey」と2年連続で韓国大衆音楽賞にノミネート。『Jarasum Jazz Festival』や『Asian Pop Festival』など韓国の主要フェスにも出演し、その存在感を着実に増している。
さらに、バンドの枠を超え、レーベル運営やフェス、コミュニティ活動なども自ら率先して手がけ、あらゆるものを繋ぐハブとして、シーンに新たな広がりをもたらしている点も見逃せない。
そんな要注目バンド、Soul deliveryが10月8日(水)に東京・青山月見ル君想フのステージに登場する。本記事では、来日公演を目前に控えた彼らのメールインタビューをお届け。即興的で予測できない瞬間を楽しむ彼らだが、語られる言葉の端々には必然的にたどり着いた思考やビジョンがにじむ。そのあいだにあるものを、少し覗いてみよう。
1. 読者の皆さんに向けて、バンドの自己紹介をお願いします。
Jeong Yonghoon:こんにちは。私たちはソウルミュージックという共通の関心を持つ4人のメンバー、SHINDRUM、HAEUN、Jeong Yonghoon、Joon’s Second Lifeで結成したバンドです。ジャムセッションを通して即興的で自由な方法で音楽を作り、3枚のフルアルバムと1枚のリミックスアルバム、そして最近は踊れる楽しいグルーヴのシングル曲をリリースしています。
「Soul Delivery」という名前はソウルミュージックへの関心から生まれたものであり、同時に私たち自身のソウル(魂)も意味しています。そして、パンデミックの時期に韓国でデリバリー文化が重要な生活様式として定着したように、音楽を通して私たちのソウルを人々に届けたい、そんな想いを込めています。
2. 音楽やアティチュード面で影響を受けた人物、アーティストについて教えていただけますか?
SHINDRUM:僕にとって、クエストラヴは今もなお学びの源泉です。彼のおかげで、ソウルクエリアンズのコラボレーションの可能性やジャムセッションをベースにした実験精神が、僕の思考を一変させました。インターネットが広く普及し始めた初期に、彼がザ・ルーツのプロモーションのために立ち上げたウェブサイト「Okayplayer」は、すぐにヒップホップ初期のオンラインコミュニティ/フォーラムのハブへと成長しました。さらに進んで、『Roots Picnic』という音楽フェスを通じて、ヒップホップやネオソウル、ブラックミュージックシーンのローカルかつグローバルなハブとしての役割を担い続けています。そして、フードと音楽を融合させたプロジェクトが、どのようにしてコミュニティへと発展していくのか、その過程を目の当たりにすることができました。そのほかにも、カリーム・リギンスの作品を通して、ドラミングとサウンドデザインの創造性がどれほど広く拡張できるのかを知りました。
そのため、ここ数年はSAULTの動向に大きな関心を持っています。彼らは「形式そのものがメッセージである」という姿勢で、それが総合芸術として大きなインスピレーションを与えてくれるんです。
また、その間に僕はスタジオ「RSS HOUSE」を建てることになり、建築家ル・コルビュジエについて知りました。特にピュリスム(不必要なものをそぎ落とし、純粋な形態と秩序を明らかにする姿勢)は、今の僕に非常に必要なものだと感じています。
Jeong Yonghoon:本当にたくさんいるのですが、人生における大きな転機を挙げるとすれば、まずディアンジェロとソウルクエリアンズですね。19歳の時に初めてディアンジェロの「Untitled (How Does It Feel)」を聴いてブラックミュージックに深くのめり込み、それをきっかけにさらに幅広く音楽を知るようになりました。ネオソウルやヒップホップをもっと聴き込み、ソウルミュージックにも興味を持つようになり、R&Bやブルース、アフリカ音楽など、彼らが影響を受けた音楽や文化を知ったことが、今の僕の価値観に大きな影響を与えました。Soul deliveryも彼らの音楽の作り方から深くインスピレーションを受け、ジャムセッションで音楽を作るようになったと思います。
Soul deliveryを結成した頃にはジャイルス・ピーターソンを知り、子どもの頃に聴き込んでいたアシッドジャズと現在のUKジャズシーンについて詳しく知ることになり、音楽のスペクトラムがさらに一段と広がるきっかけになりました。彼が2024年に韓国のクラブ・MODECiに来た際、実際にお会いして大きな感動を覚えました。
HAEUN:夢を与えてくれたアーティストは数えきれないほどいますが、最近は “レガシー” について考えることが多くなりました。自らのレガシーを地道に積み上げ、伝説となったアーティストの活動を調べたり聴いたりしています。Rhodes、Wurlitzer、JUNO-106といったアナログキーボードを扱うようになり、以前は理解できなかったサウンドがわかるようになったことで、ハービー・ハンコックのアルバムや彼の挑戦的なサウンドから大きなインスピレーションを受けています。YMO時代の坂本龍一さんも大好きです。坂本さんも当時、ハービー・ハンコックから多くの影響を受けたと聞いています。私もキーボーディストとしてのレガシーをどう受け継ぎ、先輩方から受けた影響を独自の色でどう表現していくか、常に模索しています。最近はピート・ジョリーやファラオ・サンダースのようなスピリチュアルジャズのアーティストにも興味があります。
それから、女性アーティストとして生き残っていくことについても、悩みが多いのも事実です。だからこそ女性ミュージシャンが大好きで、中でも私がロールモデルとして目指しているアーティストがソランジュです。彼女のアルバム『A Seat at the Table』を聴いたときの衝撃は、今でも鮮明に覚えています。ミニマルなサウンドを追求しつつも、最も自分自身に正直な意味を込めたこのアルバムは、これからもずっと私の中で1番であり続けると思います。ソランジュの持つ美的センスやコミュニティも、私が最も手本にしたい部分です。音楽を武器に、さまざまなアートと結びつけた作品を生み出すのが、私の長年の夢でもあります。近い将来、私自身のプロジェクトを通して、ソランジュが歩むような先駆者としての役割を担うことができたらと思っています。
Joon’s Second Life:影響を受けたアーティストは本当にたくさんいますが、その中のひとつを挙げるなら、SAULTだと思います。デビューアルバムが出た頃から最近の『All Points East』でのライブまでずっと追いかけているんですが、既存の音楽マーケットの公式を壊そうとする姿勢がとても印象的です。もちろんその過程で雑音もありますが、今このシーンで最も目立つ動きをしているチームのひとつではないかと思います。僕自身もSoul deliveryで、音楽業界の既存の秩序を壊してこれまでやりにくかったことに挑戦したい気持ちが強いので、SAULTの歩みを見るととても勇気をもらえます。
3. バンド結成の経緯をお聞かせください。本格デビューはコロナ禍の2022年1月だったと思いますが、活動をスタートするにあたり、その時期の行動制限や社会状況による影響はありましたか?
Joon’s Second Life:当時僕はロンドンに住んでいたんですが、一時的に韓国に戻っていたところ、コロナの影響でロンドン行きの飛行機がキャンセルになったんです。せっかくなので韓国で仲間とコンテンツを撮ったり、ジャムをしたりしたくて人を集めたんですが、みんな仕事に疲れていて「自分の音楽をやりたい!」という気持ちが強かったんです。コロナで予定もほとんどなかったので、自然に地下スタジオでジャムをしながら曲を作るようになり、気づけばフルアルバムを出せるくらいの規模になっていました。その後、僕が再びロンドンに戻らなければならず、メンバーは韓国に住んでいたため、いずれにせよ1stアルバムのライブ活動はできない状況でした。むしろ、コロナのおかげで集まって作業する時間ができ、集中してアルバムを作ることができたと思います。
4. レーベル「RSS RECORDS」、音楽フェス『RSS MUSIC FESTIVAL』、スタジオ「RSS HOUSE」の運営、ポッドキャスト番組『NOGARI』など、音楽制作以外の活動も活発に行われていますよね。多岐にわたる活動の意図やそれぞれに共通する思いについてお伺いしたいです。
SHINDRUM:実は、「RSS RECORDS(Rhythm. Hope/Love)」は僕個人の活動から自然な流れで始まりました。2016年、軍服務中に「SHINDRUM X KIMGUITAR」というデュオで最初のEPをリリースしたとき、仲間たちのおかげで、音楽以外にも帽子、カバン、水筒、プロフィール写真に至るまでセルフブランディングを経験できたんです。その後、僕の1stフルアルバム『Who I Am』を制作しながら、HAEUNと一緒にCD、レコード、Tシャツ、水筒、フーディー、ステッカーなどのグッズを自分たちで制作しました。その時、「なぜかっこいい音楽ノートがないんだろう?」という疑問が生まれ、A5サイズの音楽ノートを発売したのがこのブランドの始まりです。
僕だけでなく、僕のようなアーティストたちが芸術活動に集中できる環境をつくることが、今の僕たちに必要だと思いました。活動を続けるうちに、韓国ではアーティストが立てるステージが絶対的に不足していることを実感し、それなら自分たちで場をつくろうと『RSS MUSIC FESTIVAL』を始めたんです。音楽だけでなくさまざまなブランドやシーンを繋ぎながら、持続可能な活動のあり方を模索しています。
「RSS HOUSE」は単なるレコーディングスタジオを超えた、公演・カフェ・コミュニティが融合した複合文化空間です。毎月「RSS Jam Session」、「RSS Pharmacy」(ヨガ+音楽、トークプログラム)、「NUGS GOG.o」(アーティストと関係者のコミュニティプログラム)といったプログラムを開いています。地下のレコーディングスタジオは、従来の韓国の商業スタジオ特有の堅苦しさから来る不自然さをなくし、アーティストたちが最大限クリエイティビティを発揮できるような良いバイブスを作り出すことを目指しました。また、さまざまなヴィンテージ機材(シンセサイザー、アンプ、ドラムなど)も取り揃えています。
また、独立ミュージシャンを扱うメディアが不足しているという問題意識から、エディターのgedaと一緒に「NUGS」マガジンを作り、その後、KBS、Spotify Koreaと協業してポッドキャスト『NOGARI』を始めました。これは、インタビュー、トーク、ライブを通じてアーティストとシーンの話を記録し、外部へと繋げるチャンネルです。
このように、レーベル(ブランド)、空間、フェスティバル、メディアへと続く活動は、最終的にすべてがひとつに繋がっています。音楽・空間・人が互いに有機的に結びついてこそシーンが持続可能である。この信念が、僕たちのすべての活動を導いているんです。
5. 音源とライブ演奏でのアレンジや表現の違いは、どのように生まれると思いますか?
SHINDRUM:僕たちは基本的にジャムバンドなので、お客さんとのコミュニケーションが一番大事なポイントです。ライブに来てくださる方は、ただ音楽を聴くのではなく、僕たちと一緒に即興を作り上げていく仲間のように参加してくれます。だから、毎回ステージが新しくなるんです!特にポッドキャスト『NOGARI』を始めてからは、ステージで演奏するだけでなく、気軽に会話をしたりお客さんと直接やり取りする瞬間が増えました。そうした交流が即座に演奏に反映されて、音源では聴けないライブならではの揺らぎや変化が自然に生まれているんだと思います。
Jeong Yonghoon:僕らはすべてのライブで即興なので、いつも新鮮で違ったものになるんです。それ自体を楽しんでいますね。最近リリースした「Chicken Disco」は2年前に作った曲ですが、ライブで演奏するうちに何十ものバージョンが生まれました。リリース後のライブでもブレイクを長く取ったり、演奏中に出たパターンが気に入ればそれだけを繰り返したり。お客さんが盛り上がっている部分をもっと長く伸ばして一緒に踊ることもあります。お互いの演奏には常に耳を傾けていますよ。
HAEUN:音源とライブの違いこそが、音楽を聴く楽しみのひとつだと思います。大小さまざまなライブを重ねる中で、ライブ前の自分の心の状態やバイブスがとても大事だと感じるようになりました。新しい曲を録音するときも同じです。もちろん、気分があまり良くないときでもポーカーフェイスを保つことは大切な要素のひとつです!でも、自分の状態よりもっと大事なのはお客さんが今の私たちの音楽に興味を持ってくれているかどうか。それによって、ライブのクオリティが決まると思います。
私たちも最初の頃はカッコいいアーティストに見せたくてMCを入れなかったり、曲名もきちんと伝えなかった気がします。でも今は、私たちがカッコよく見えることよりも、聴いてくれる人の関心や興味を高めるために、お互いにたくさん会話をするんです。ポッドキャストを進行するように、全体の雰囲気を自然に作っていけるよう努力しています。
Joon’s Second Life:ライブは本当に特別な体験です。特にオーディエンスとのコミュニケーションがとても大切で、その日の会場の雰囲気やお客さんの反応がライブを決めます。だから毎回違うステージを観たいと、複数公演に来てくださるファンの方も多いんです。ある日はメンバーが少し酔っていたり、楽しいことがあったり、お客さんがすごく盛り上がってくれたりすると、その場のインスピレーションで全く新しい展開に進むこともあります。それが即興演奏の魅力だと思います。「Heatwave」という曲は、ライブ中に楽器が一瞬休むところでお客さんが「Yeah!」と叫び始めて、それ以来ずっとファンの方々と一緒に作り上げている曲になりました。
6. 今注目している日本のアーティストやモノ、コトはありますか?
SHINDRUM:深く突き詰める日本の職人精神にとても興味があります。カルチャーやトレンドについてはまだあまり詳しくないので、これから学んでいきたいです。
Jeong Yonghoon:CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUINや、以前日本公演で出会ったManda、 ASOUNDといった若いミュージシャンに関心があります。お互いの国を行き来しながら交流できる場がもっと増えればいいですよね。
HAEUN:去年、済州島で開催された『Stepping Stone Festival』でOriginal LoveやSCOOBIE DOの先輩方にお会いしました。「音楽が良いね」と声をかけてくださったんです。ステージを拝見して「ああ、こういう風に年を重ねたいな」と思いました。今でもその方々の音楽を時々聴いています。日本でツアーをすると、多くの日本の先輩方にお会いしますが、皆さんいつも私たちを応援し、愛を送ってくださいます。
RSS HOUSEがソウル郊外にあるので、首都の中心を離れて黙々と自分の色を出しながら長く続いている日本のショップを訪れるのが好きです。これまで東京旅行では渋谷を中心にあちこち回っていましたが、最近は都心から少し離れたところにできた 「SKWAT/twelvebooks」というアートブックのセレクトショップに行ってきました。やはりたくさんの刺激を受けて、旅行中に何度も足を運びたくなる場所です。
Joon’s Second Life:Soul deliveryを始める前からロンドンでよくWONKを聴いていました。私の好きなモーダルなコードや実験的なソウルリズムにとても共感しましたし、メンバーがプロデュースやエンジニアを兼ねているところもSoul deliveryと似ていると思います。いつか一緒に作品を作ってみたいです。1stフルアルバムを作っているときには、冨田恵一さんのMIXTAPEもよく聴いて、メンバーと一緒にインスピレーションを受けていました。それ以外にも、すでに有名ですがSweet Soul Recordsの活動も好きですし、以前ロンドンでYokohama Callingを通じて出会った福盛進也さんや井上銘さんも大好きな演奏家です。日本のジャズシーンの若いプレイヤーとももっと交流したいですね。
7. 最後に、日本公演での抱負と、日本のファンに一言お願いします!
SHINDRUM:日本に行くたびにファンの皆さんの表情や身振りが鮮明に蘇ります。今回のツアーでも素敵な思い出をたくさん作りましょう!ありがとうございました。
Jeong Yonghoon:日本の公演では、いつも最高のバイブスを思い出します。今回お会いする日本のオーディエンスの皆さんとも、また一緒に素敵な思い出を作りたいです。オープンな気持ちでお会いできる日を心待ちにしています。「またすぐに会いましょう(日本語で)」。
HAEUN:私は「さいこ(最高)」という日本語の言葉が好きです。初めて聞いたときは、私に向かって「psycho」と言っているのかと思いました(笑)。意味を知ったら、すごく可愛い言葉だなと思いました。皆さんが私たちに「さいこ!」と叫んでくださる瞬間が一番幸せです。私も皆さんに向かって叫びたいです!必ず会いましょう!
Joon’s Second Life:音楽は国境を越えるコミュニケーションの言葉ですよね。ぜひライブで一緒に音楽を通じて交流しましょう。最後まで読んでくださって本当にありがとうございます!
Writers
- Akari Hiroshige(BUZZY ROOTS)